抗がん剤(化学療法)
抗がん剤治療(化学療法)と副作用:非小細胞肺がん、小細胞肺がん
非小細胞肺がんの抗がん剤治療
ステージ3では放射線治療と組み合わせておこないます
手術が適応とならないⅢ期(ステージ3)の非小細胞肺がんの患者さんに対しては、胸部への放射線治療と抗がん剤の併用療法(化学放射線療法)が標準治療です。白金(プラチナ)製剤と他の抗がん剤を決められたスケジュールで点滴します。4週間を1サイクルとして2回繰り返す、週に1回の投与を6回繰り返す等、薬の種類によって異なります。化学放射線療法で進行の無かった患者さんには、維持療法として免疫チェックポイント阻害薬による治療を選択することができます。維持療法は4週間に1度、1年間おこなうことが勧められています。
また、EGFR遺伝子変異陽性の肺がんと診断され、化学放射線療法で進行の無かった患者さんに対する維持療法として、分子標的薬であるEGFR阻害薬での治療も選択できます。
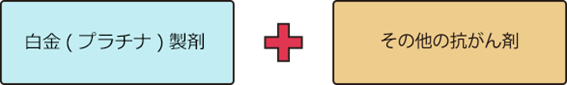
ステージ2~3の一部では抗がん剤や免疫チェックポイント阻害薬、分子標的薬を用います
Ⅱ期~ⅢB期(ステージ2~ステージ3B)の患者さんでは、手術前後に抗がん剤や免疫チェックポイント阻害薬を用いることがあります。Ⅱ期~ⅢA期(ステージ2~ステージ3A)の患者さんで、EGFR遺伝子変異が陽性の場合は、術後の抗がん剤治療後に、分子標的薬であるEGFR阻害薬を3年間続けることが勧められています。
ⅢB/C期(ステージ3B・ステージ3C)の一部では抗がん剤や免疫チェックポイント阻害薬を用いた薬物療法が治療の中心となります。抗がん剤治療には、白金(プラチナ)製剤と他の抗がん剤を組み合わせたプラチナ併用療法がおこなわれます。
ステージ4では遺伝子変異に応じて分子標的薬での治療もおこないます
Ⅳ期(ステージ4)では、個々の患者さんの遺伝子変異に合わせた分子標的薬での治療や、抗がん剤と免疫チェックポイント阻害薬を組み合わせた治療がおこなわれます。薬の種類によって3週間~6週間に1度おこなわれます。
二次治療では種類の異なる抗がん剤を使います
1回目の抗がん剤で効果がみられなかったり、治療後に病気が悪化したときには、二次治療として1種類の抗がん剤による治療がおこなわれます。全身状態が良好であれば、前回とは抗がん剤の種類を変更することが検討されます。
近年では抗がん剤の種類が増えたため、三次治療、四次治療と薬剤を変えて治療が続けられることも少なくありません。
小細胞肺がんの抗がん剤治療
小細胞肺がんは進行が速いため、手術ができる早期のうちに見つかることが少なく、薬物療法や放射線治療が中心となり、手術がおこなわれることはまれです。そのため、他のがんのようなI期~Ⅳ期という病期分類(ステージ)はあまり使われません。
また、小細胞肺がんは非小細胞肺がんに比べ、抗がん剤による効果が得られやすいため、抗がん剤が治療の主体となります。早期であっても手術単独ではなく、抗がん剤を併用することが勧められています。
病期分類と治療法
限局型:化学放射線療法。手術ができる場合は手術後に抗がん剤治療
2025年からは、化学放射線療法後に、再発予防のために維持療法として免疫チェックポイント阻害療法を選択することができるようになりました。
進展型:抗がん剤治療単独、抗がん剤+免疫療法併用
小細胞肺がんについては、治療方針を決めるために「限局型」「進展型」のどちらのタイプかを分類します。
臨床成績
限局型小細胞肺がんで「化学放射線療法」をおこなった80~90%の患者さんのがんが縮小し、約半数でがんがほぼ消失します。
抗がん剤治療で起きやすい副作用
副作用は使うお薬の種類によって異なり、個人差もあります
薬物療法(抗がん剤治療)による副作用の種類や頻度は、使うお薬の種類によって異なります。なお、よくみられる副作用としては、吐き気・嘔吐、食欲不振、口内炎、下痢、便秘、全身倦怠感、末梢神経障害(手足のしびれ)、脱毛等があります。自分で症状を感じられる副作用の他に、白血球減少、貧血、血小板減少等の検査でわかる副作用や、肝機能障害、腎機能障害、心機能障害、肺障害等の検査したほうがわかりやすい副作用もあります。副作用の程度には個人差があり、まれに重い副作用で命にかかわることもあります。
こうした副作用のほとんどは一時的なもので、大部分は治療後2〜4週間で回復します。吐き気や嘔吐は薬を使った後の数日間を中心に起こります。脱毛と末梢神経障害は数ヵ月かかりますが、徐々に回復します。
注射やお薬を飲んで副作用の症状をやわらげます
白血球が大きく減っている場合は、細菌などによる感染症にかかるリスクが高くなりますので、白血球増殖因子(G-CSF)と呼ばれる白血球を増やす薬を注射することがあります。
ひどい貧血が起こったり血小板が大きく減少したりしているときは輸血をおこなうこともあります。吐き気や嘔吐には吐き気止めの薬を使います。末梢神経障害に対する効果的な治療法は残念ながら今のところありません。
脱毛については、予防のため抗がん剤投与中に頭部を冷却する方法が考えられていますが、まだ研究段階であり、実施している施設はわずかです。
参考:
・日本肺癌学会編:肺癌診療ガイドライン2024年版, 金原出版株式会社
・日本肺癌学会編:患者さんと家族のための肺がんガイドブック2024年WEB版
監修:日本医科大学 呼吸器・腫瘍内科学分野
教授 笠原寿郎先生
2022年12月掲載/2025年9月更新