手術療法
肺がんの手術の実際と手術前後の治療
入院や手術は誰しもが緊張し不安になるものです。経験がないと入院してからの流れがわからないため、さらに不安を感じる方もいらっしゃるかもしれません。下記は手術前の検査から退院までの一般的な流れです。
実際の流れは、各施設により異なることがありますので、おかかりの施設にご確認ください。
■手術の流れ
手術前の検査
肺がんであることが確定した後、がんの広がりを調べ、病期(ステージ)を決めるために、胸部造影CT検査、PET検査、骨シンチグラフィ、腹部CT検査またはエコー検査、頭部CT検査またはMRI検査等を行い、手術が適応できるかを調べます。手術ができる場合は、さらに、全身状態や病歴、血液検査、呼吸機能検査、心電図検査等を行い、手術に耐えられる体力があるかどうか等を評価します。
入院準備
持病のコントロール
高血圧症や糖尿病等の持病がある場合は、手術中、術後の合併症のリスクが高まるため、手術の前に病状のコントロールをおこないます。
また、血栓予防薬のように、手術前にあらかじめ服用を中止しておかなければならない薬がありますので、服用している薬がある場合は担当医に伝えましょう。
禁煙
喫煙していると、術後に痰が多くなることで痰が気管支に詰まり、肺炎等の合併症のリスクが高まります。また、術前や術後の薬物療法(抗がん剤や免疫チェックポイント阻害薬)の効果も上がりにくくなりますので、治療が決まったら直ちに禁煙します。禁煙の手助けがほしい場合は、「禁煙外来」を受診することもできます。
口腔内のメンテナンス
全身麻酔の際に気管チューブを口から挿入するため、抜けそうな歯がないか、歯科でチェックしましょう。
呼吸リハビリテーション
手術前から、呼吸リハビリテーションを取り入れて基礎体力を高めておきます。呼吸リハビリテーションによって体力づくりをしておくと、手術後に起こりやすいトラブルを防いだり、軽くしたりすることができます。
入院時の持ち物
入院手続きに必要な書類や健康保険証、印鑑等が必要です。身の回りの物を含め、入院時に必要な持ち物や手続きについては病院で説明書を用意していることが多いので、確認してみましょう。また、あらかじめ「限度額適用認定証」を取得しておくと、窓口での支払い金額を抑えることができます。取得したい場合は、病院の医事課やがん相談支援センターに相談して、加入している医療保険に申請しましょう。
入院から手術まで
手術の数日前に入院することが多いです。
入院すると担当の看護師から入院生活についての説明を受けます。また、手術後の体の動かし方や呼吸の仕方、痰の出し方等を教わることもあります。術前オリエンテーションでは担当医から手術の内容や流れ、予定時間等について説明を受けます(入院前におこなわれることもあります)。麻酔についても、通常は手術の前日までに麻酔科医から説明や問診を受けます。手術前日には入浴やシャワーで体を清潔にしておきます。
食事は、手術前日の夕食まで食べられることが多いですが、手術の内容によっては水分や食事が制限される場合もあります。
手術前日は手術当日の朝に排便できるように下剤が処方されることが多いです。緊張や不安等で眠れない場合は、睡眠導入薬が処方されることもありますので、担当医や看護師に相談しましょう。
手術当日
手術当日は食事ができません。水分もとれず、うがいだけ可能です。手術室へ向かう準備をしながら、時間までできるだけリラックスして過ごしましょう。
手術室へ
眼鏡やコンタクトレンズ、入れ歯、アクセサリー等はすべて外します。下着を脱ぎ、手術着に着替えます。
手術中と手術前後の全身管理のため点滴を受けます。手術室へは歩いていくこともありますし、車いすやストレッチャーに乗って向かうこともあります。
手術室に入る前に手術用キャップをかぶり、名前やリストバンドにより本人確認をされます。
手術台に移動すると、心臓や呼吸を管理するためのモニターが取り付けられます。感染を防ぐために手術部位の消毒がおこなわれ、大きな布で体が覆われます。
麻酔
術後の痛みを抑えるため、硬膜外麻酔のチューブを挿入し、術後数日間持続的に麻酔薬を投与できるようにします。硬膜外麻酔のチューブは横向きになり、丸めた背中から挿入します。痛み止めを注射した後におこないますので、痛みよりも背中を押される感じがすることが多いです。
その後、全身麻酔がおこなわれます。酸素吸入器を口に当てられ、呼吸をしているうちに全身の力が抜け、眠りに入ります。
意識がなくなった後、口から気管チューブが挿入され、肺に酸素が送られます。十分に麻酔がかかった後、手術が開始されます。
手術
肺がんの手術時間は内容によっても異なりますが、2~4時間程度です。
意識がもうろうとしているかもしれませんが、手術が終わったら呼びかけられますので、名前を呼ばれたら返事をします。
意識が戻り、呼吸ができるようになったら気管チューブが取り除かれます。肺を切除した部分にたまる血液や体液等を排出するためのドレーンや尿をためる袋につながるバルーン、点滴、硬膜外麻酔のチューブ等、体にはさまざまな管が装着された状態になっており、煩わしさを感じるかもしれません。また、痛みや長時間横になっていたことによるしびれ等があるかもしれませんが、無理に動かさず、要望があれば看護師に伝えましょう。
手術から退院まで
術後の痛みや息苦しさ
術後は切除した手術部位やドレーンを入れた部位等に痛みが生じますが、術後2日間くらいは強い痛みが出ないように硬膜外麻酔を継続します。それでも痛みを感じるときは遠慮せずに医療スタッフに話し、鎮痛剤を処方してもらいましょう。術後の痛みは直後が最も強く、徐々に軽くなって、1週間後くらいには日常生活に支障がなくなるといわれています。
手術の際に挿入した気管チューブにより気管支に違和感が残り、咳が出やすくなったり、分泌物等で息苦しくなったりすることがあります。また、肺や気管支を切除することで呼吸機能が低下するため、しばらくは息苦しさが生じます。対策として、換気や温度、湿度の調節等をおこなうことにより、呼吸が楽になることがあります。息苦しさを早く解消できるよう、呼吸筋を鍛えるための呼吸リハビリテーションをおこなうことが大切です。また、歩行練習等で全身の筋肉を鍛えることも呼吸筋の回復に役立ちます。症状がつらいときは我慢せず、担当医や看護師に相談しましょう。
術後の経過と回復
術後の経過は傷口の大きさや回復力等により異なるため、あくまで目安ですが、元気な患者さんでは手術の次の日に歩けるようになります。
術後2~4日目くらいにはドレーンやバルーン等の管を抜き、廊下を歩くことができるようになります。
その後は病院内を歩いたり、シャワーを浴びたりすることができるようになります。食事も回復の状況に合わせて、徐々に点滴だけの状態から元の食事に戻ります。
術後1週間は手術による合併症が起こりやすい時期ですので、注意が必要です。あまり神経質になる必要はありませんが、気になる症状があるときは担当医や看護師に相談することが大切です。
退院
術後1週間くらいで退院できることが多いです。
手術からの回復状態を確認する必要がありますので、次の受診日を確認しましょう。
■手術前後の治療
手術前に薬物療法(ネオアジュバント療法)をおこなう理由
肺がんの手術前に、がんを小さくし、わずかな転移を防ぐ等手術の効果を高める目的で薬物療法をおこなうことがあります。
手術前の薬物療法はネオアジュバント療法と呼ばれ、非小細胞肺がんのⅡ期~ⅢB期(ステージ2~3B)の患者さんに検討されます。使用される治療法は、白金(プラチナ)製剤を併用する抗がん剤による化学療法、抗がん剤と免疫チェックポイント阻害薬であるPD-1/PD-L1阻害薬を併用する方法、化学療法と放射線治療の両方をおこなう化学放射線療法があります。
手術後に薬物療法(術後補助療法)をおこなう理由
手術により目で確認できる範囲のがん細胞のすべてを取り除くことができても、顕微鏡レベルではがん細胞が一部、身体の中に残っている可能性があります。そこで、切除した肺やリンパ節を顕微鏡で調べた結果「病理病期」が新たに確定され、それにもとづいて手術後の治療方針を検討します。
一度、肺がんが再発すると完全に治すことが難しくなります。そのため、再発や転移を予防するために、手術の後に全身療法である化学療法をおこなうことがあり、それを術後補助化学療法といいます。
非小細胞肺がんでは病理病期のⅠA3期、Ⅱ期、ⅢA期、限局型小細胞肺がんの場合はⅠ期、ⅡA期で、いずれも手術によりがん細胞を完全に取り除くことができたと思われる場合におこなわれます。
また、ⅡA~ⅢB期(ステージ2A~3B)の非小細胞肺がんの患者さんには、術後に免疫チェックポイント阻害薬を単独で投与する治療法もおこなわれるようになりました※。
術前、術後のいずれも、治療をおこなうべきかどうか、どのような薬剤を用いるかは、がん細胞の種類や進行度等によっても異なります。主治医の説明をよく聞き、相談して決めましょう。
- ※:術前・術後補助療法における術後補助療法として用いる
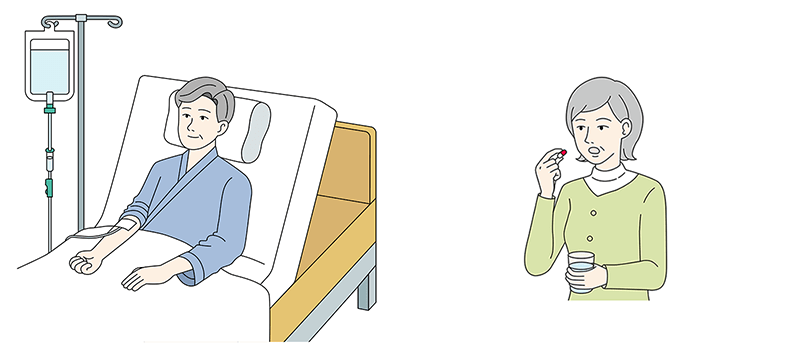
監修:日本医科大学 呼吸器・腫瘍内科学分野
教授 笠原寿郎先生
2022年12月掲載/2025年9月更新