放射線治療
肺がんの種類・病期による放射線治療
早期非小細胞肺がんでの放射線治療
がん細胞に放射線を照射して、がんを死滅させる治療法です。Ⅰ期~Ⅱ期で何らかの理由で手術をおこなわない場合、放射線治療が勧められています。一方、手術が可能であっても、十分な範囲の切除が難しい場合には、手術前に放射線治療をおこなうこともあります。
放射線治療は研究開発が進み、さまざまな照射方法がありますが、早期(Ⅰ~Ⅱ期)の非小細胞肺がんの患者さんには、「定位放射線療法(ピンポイント照射)」が勧められています。特に「SBRT(体幹部定位放射線療法)」や「粒子線治療(陽子線治療・重粒子線治療)」等、高い線量を集中させてがんを攻撃する高精度な照射方法を用いることが勧められています。
- ※従来、先進医療としておこなわれていた重粒子線治療・陽子線治療は、2024年6月よりⅠ期~ⅡA期について保険適用となりました。
Ⅲ期非小細胞肺がんでの放射線治療
縦隔のリンパ節に転移がある場合や、手術で完全にがん病巣を取り除くことが不可能な場合および体力的に手術に耐えられないと判断された場合と、ⅢB/C期(ステージ3B・3C)の非小細胞肺がんで化学放射線療法の適応と判断された場合には、手術ではなく化学放射線療法が治療の第一選択になります。治療後に「維持療法」として免疫チェックポイント阻害薬を4週間に1度、1年間継続します。がんの遺伝子検査の結果、EGFR遺伝子変異陽性の肺がんと診断された場合は、治療後にEGFR阻害薬での治療も選択できます。なお抗がん剤(化学療法)での治療が難しい場合は放射線治療単独での治療が推奨されています。
早期以外の非小細胞肺がんでは、リンパ節等早期よりも広い範囲への放射線照射が必要となるため、「三次元原体照射(3D-CRT)」や「強度変調放射線治療(IMRT)」も用いられています。
なお胸水がたまっている等の症状があるときは、放射線治療は第一選択にはなりません(症状をやわらげるための放射線治療は考慮されます)。
非小細胞肺がんの化学放射線療法は、通常分割照射法(1日1回、月曜から金曜までの週5回)で、患者さん個々の体調を見ながら、できるだけ合計60Gy(30回)以上の照射をおこなうことが推奨されています。
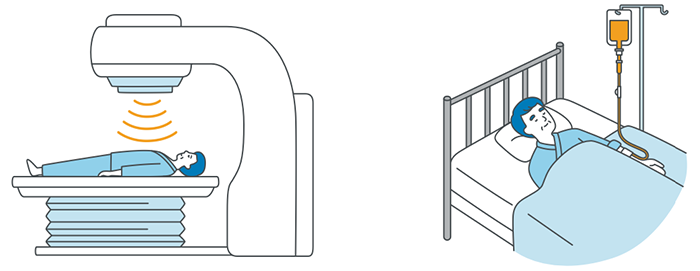
限局型小細胞肺がんでの放射線治療
限局型小細胞肺がんと診断され、手術よりも他の治療法が適していると判断された場合の標準治療は、抗がん剤と放射線治療の併用(化学放射線療法)です。
化学放射線療法
限局型小細胞肺がんの速い進行を抑えるため、抗がん剤を併用しながら「加速過分割照射法(45Gy/30回/3週)」をおこないます。この方法では約3週間、1日2回の頻度で放射線を照射します。ただし、身体の状態やがんの場所等で放射線治療の副作用が懸念される場合には、1日1回の治療を約6週間続けることもあります。
再発・転移を防ぐ追加治療
限局型小細胞肺がんは比較的再発しやすいという難点があります。そこで、化学放射線療法で効果が十分に得られた患者さんを対象に、免疫チェックポイント阻害薬(PD-L1阻害薬)による追加治療が選択できるようになりました。
- ※免疫チェックポイント阻害薬(PD-L1阻害薬)の使用は2025年春より可能になりました。
また、脳への転移を防ぐために、脳全体への放射線照射(予防的全脳照射 PCI:ピーシーアイ )もおこなわれます。予防的全脳照射(PCI)は化学放射線療法で良好な治療効果が確認されてからできるだけ早期(治療開始から6ヵ月以内)におこなうことが望ましいとされています。
1回あたりの線量は2.5Gyの照射を10回相当用いることが勧められています。治療期間は約2週間です。(医療施設により異なる場合があります)
- ※予防的全脳照射は、進展型小細胞肺がんの患者さんに対しては効果が確認されておらず、現在推奨されていません。
参考:
・日本肺癌学会編:肺癌診療ガイドライン2024年版, 金原出版株式会社
・日本肺癌学会編:患者さんと家族のための肺がんガイドブック2024年WEB版
監修:日本医科大学 呼吸器・腫瘍内科学分野
教授 笠原寿郎先生
2022年12月掲載/2025年8月更新